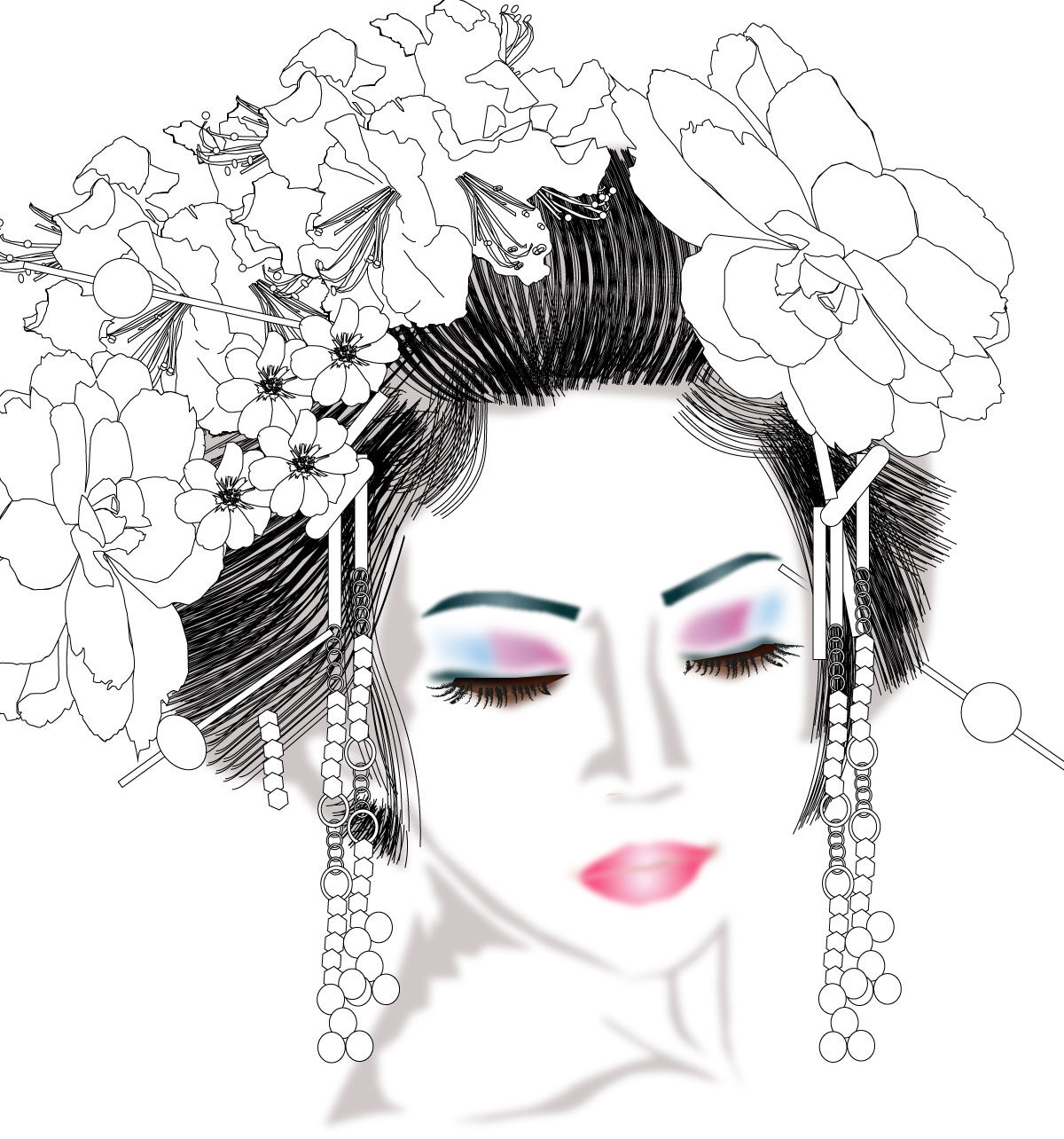テープかぶれの原因と予防・改善策を解説!
こんにちは、臨床化粧療法士®︎、看護師の谷井香菜です。
皆さんは、皮膚に貼って使うお薬があることをご存知でしょうか。
口から飲む薬と比べて、飲み忘れをしにくくなることや血中濃度を安定させるなど、様々なメリットがあり、精神科や婦人科領域でも使用されています。
しかし、薬を貼っている肌の部分が赤くなったり痒くなってしまうことも珍しくありません。
特にこの暑い時期は起こりやすいです。
今回は、貼付剤などで起こるテープかぶれについて考察していきたいと思います。
テープかぶれ・痒みの原因
テープによるかぶれや痒みは、多くの人が経験する皮膚のトラブルの一つです。
この不快な症状は、単なる不適切な貼り方だけでなく、さまざまな原因によって引き起こされます。
まず、皮膚が炎症を起こすことによって痒みが生じるケースが非常に一般的であり、その背景にはアレルギー反応や肌への刺激が関係しています。
原因としては大きく3つに分かれます。
①アレルギー反応による皮膚の炎症
テープに含まれる粘着剤や添加剤などがアレルゲンとなることが多く、これらが皮膚の表面に触れると免疫反応が活性化され、皮膚の赤みや湿疹、ヒリヒリとした刺激感・痒みを伴うと言われています。
これらの症状は、一度だけではなく繰り返しテープを貼ることでも悪化し、慢性的な皮膚炎へと進行することもあります。
特に、敏感肌やアレルギー体質の人は注意が必要です。
アレルギー性の炎症は放置すると皮膚のバリア機能を低下させ、感染やその他の皮膚トラブルを引き起こす恐れもあります。

②皮膚への過剰な刺激と摩擦
テープによる刺激や摩擦も、痒みや肌荒れの原因として考えられます。
長時間同じ箇所に貼り続けたり、雑に剥がしてしまうと、皮膚の角質層を傷つけて炎症が起こってしまいます。
また、汗や皮脂によってテープと肌が密着した状態になると、摩擦と湿気が重なり、炎症や痒みが悪化しやすくなります。
③不適切な貼付方法
貼付剤の貼り方も、テープかぶれの根本的な原因の一つです。
例えば、貼付面が凸凹していると、貼り残しやシワができ、肌への局所的な圧迫や摩擦を引き起こします。
また、貼付面の清潔さや乾燥状態も影響します。油脂や汚れが付着していると粘着が不十分となり、肌の摩擦や剥がれやすさを招きます。
予防に効果的なケアと注意点
テープによるかぶれや痒みの不快感を軽減し、再発を防ぐためには、適切な予防策と積極的な対策が不可欠です。
正しい知識と適切な行動により、より快適な皮膚状態を維持できます。
①肌を清潔に保つ
汗や油分が残っている状態で貼ると、皮膚への刺激やアレルギー反応のリスクが高まります。
清潔に洗った後はしっかりと乾燥させ、肌の準備を整えましょう。
②同じ場所に連続で貼るのを避ける
前回貼ったところとは、位置をずらして貼ることで繰り返しの刺激を避けることができます。
③貼付位置に注意する
敏感な部位や皺になりやすい部分を避けることで、摩擦やかぶれを防ぐことができます。
⭐︎これらの予防策を習慣化することで、肌の負担を最小限に抑え、トラブルを未然に防ぐことができると考えられます。
もしもテープかぶれが起こってしまったら?
まずは日常生活の中でできる予防ケアに注目し、次に症状が現れた時に行う具体的な対策、最後に傷ついた皮膚の修復とアフターケアについて詳しく解説します。
炎症(赤み・痒みがあるとき)
冷たい湿布や冷感ジェルを患部に当てることで、血管の拡張を抑えて痒みを軽減できます。
また、市販の抗ヒスタミン剤や抗アレルギー薬を使用することも一つの方法です。
ただし、薬剤の使用は医師の指示を仰ぐことが望ましいです。
さらに、肌の乾燥を防止するために保湿ケアも欠かせません。
敏感肌用の無香料、低刺激の保湿クリームやローションを頻繁に塗ることで、バリア機能を高め、痒みの原因となる乾燥を防ぎます。
乾燥と摩擦を避けるためには、衣類も柔らかく肌に優しい素材を選ぶ必要があります。
また、掻き壊すことは逆効果です。
掻くことで皮膚の炎症が悪化し、痒みが増し、傷跡や感染症のリスクも高まります。
掻きたい衝動を抑えるために、手を清潔に保ち、爪を短く切ることも効果的です。
これらの具体的対策を継続的に行うことで、痒みの程度を抑え、症状の悪化を防ぐことができます。

効果的なアフターケア
刺激の少ない温水と無香料の洗浄料を使い、優しく洗います。
摩擦を避けるためにタオルで押さえるようにして、水分をしっかりと拭き取りましょう。
保湿ケア
洗浄し乾かした後は、即座に保湿剤を塗布します。
保湿剤はセラミドやヒアルロン酸配合の低刺激製品を選び、肌の水分保持機能を補います。
バリア機能を高め、痒みの原因となる乾燥を防ぐことができます。
衣類選び
皮膚に接触する服などの衣類は、柔らかく肌に優しい素材を選ぶことで乾燥や摩擦を防ぎます。
生活習慣の見直し
十分な睡眠とバランスの良い食事、適度な運動は、肌の自然治癒力を促進します。
これらの対策を継続的に行うことで、痒みの程度を抑え、症状の悪化を防ぐことができるでしょう。
傷や炎症がひどい場合は、抗炎症作用のある軟膏やステロイドクリームを適切に使用し、皮膚の炎症を抑えることが大切です。
医療機関を受診し医師の指示に従いましょう。
炎症が治った後は、日焼け止めを塗るなどして、紫外線から肌を守ることにより、色素沈着や瘢痕のリスクを低減させます。

まとめ
定期的に皮膚の状態を観察し、異常を感じたら早めに医療機関を受診し、適切な治療とケアを継続することが、健康な肌を維持するための最も効果的な方法です。
少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
資格講座の申し込み

「臨床化粧療法士®」になる為の資格講座やワークショップを随時開催しています。お化粧のちからで、より多くの方がいきいきと自分らしく活動できる社会を目指します。
前の記事へ
次の記事へ