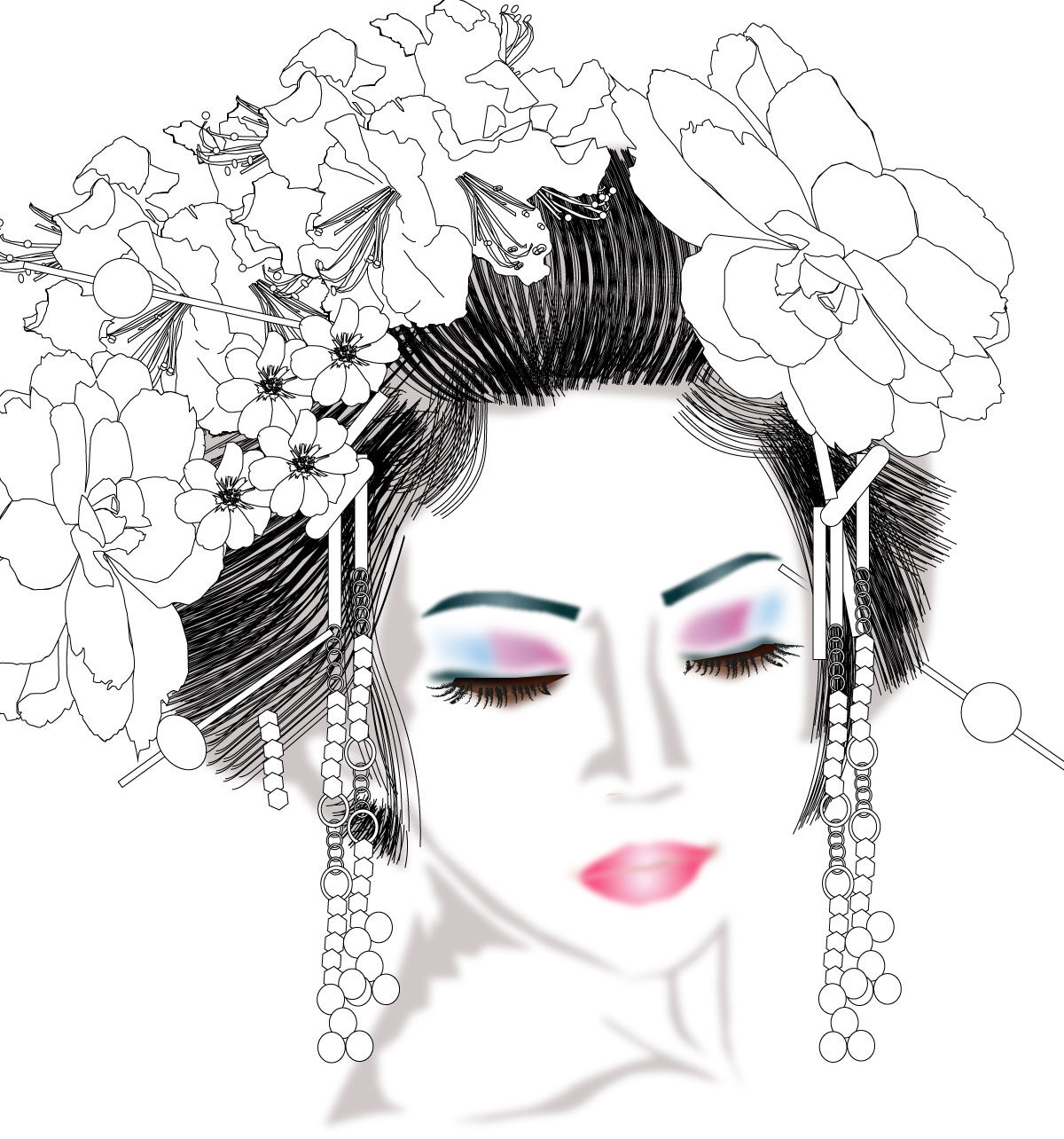入院中の身だしなみケアとリハビリの相乗効果を解説

みなさんは、「入院中の身だしなみ」と聞くと、どのようなイメージを抱くでしょうか。
私は普段、総合病院で理学療法士としてリハビリテーション業務に従事しています。
これまで私が関わった患者さんの中には、入院中にも関わらずリハビリテーション(以下:リハビリ)の前に化粧をされていたり、身なりをきちんと整えている方がいらっしゃいました。
日々臨床現場にいると、入院中の患者さんの身だしなみについて考えさせられる機会が多くあります。
そこで今回は、身だしなみを整えることと、リハビリとの関係性について詳しく解説していきます。
入院中の身だしなみを整える
病院には、検査や治療を目的とした予定入院の方や、救急搬送された緊急入院の方など、様々な患者さんがいらっしゃいます。
ただ、あくまで病院は治療が最優先の場です。
生命を脅かす状況や感染対策が目的となる最低限のセルフケアは別として、いわゆる外見の「身だしなみ」の問題は二の次になりがちです。
私は普段リハビリの際に、患者さんの寝癖が強い時や病衣の胸元が乱れていたらサッと直したり、患者さんの最低限の身だしなみは整えるように意識しています(医療者として当然のことなのかもしれませんが)。
治療に影響しない、生命の危機に晒されている状況でないことを大前提としてではありますが、身だしなみは入院生活を送る上で非常に大切なことだと考えています。
以前担当していた高齢女性の方は、骨折で緊急入院していたにも関わらず、毎朝必ず眉毛を描いて髪の毛を整えていました。
入院していてもセルフケアを忘れず、身なりを整えようという意識を持っている方は、男女問わず多くいらっしゃると日々感じています。
入院中の身だしなみは困難?

一方で、入院中は加齢や怪我、麻痺などの理由でセルフケアが思うように出来なくなってしまう場合もあります。
これは、知り合いが看護学生時代に経験したエピソードです。
認知症でしっかりとした意思疎通が取れず、表情が固くなってしまった女性と関わっていた時、毎日欠かさず顔を拭いて、髪の毛を整えていました。
ある日いつもの整容介助を終え、手鏡を持たせてあげると、その時だけ、ニコッと笑顔になったそうです。
入院中の自己管理が困難な状況が多い中でも、適切な身だしなみケアを行うことで、清潔感や自尊心が保たれ、心理的なストレスも軽減されます。
身だしなみを整えることは、心の健康にも繋がる行為なのだと思います。
身だしなみを整えるメリット

身だしなみを整えることは、清潔に保つことで感染予防になったり、入院生活にメリハリをつけたり、気分転換になったり、QOL(生活の質)の維持、向上になるなどの効果が得られます。
また、身だしなみというのは、バッチリお化粧をして、ヘアセットをして…という以前の、最低限の身なりを整えるということから始まります。
他人に見られるという意識を持つことだけでなく、自分自身の心の整理につながったり、化粧やオシャレを楽しむことに繋がる大切な過程だと私は考えています。
身だしなみとリハビリの相乗効果

では、身だしなみとリハビリにはどのような関係性があるのでしょうか。
たまに病棟などで「イケメンの〇〇先生に会うからリハビリ行く時はキチッとしないと!」などと聞こえてくることがありますが(笑)
これも、身だしなみを整えるという点ではとても大事な理由であり、リハビリは重要なモチベーションとなります。
実際に、山口ら1)の研究によると、毎朝の整髪が患者のリハビリ意欲の改善に繋がることが明らかになっています。
病院や介護施設において、身だしなみのケアとリハビリは、患者さんの回復を促進するために密接に関連しています。
適切な身だしなみを保つことは、患者の自己肯定感や精神的安定を高め、リハビリへの積極的な取り組みを引き出す重要な要素です。
一方で、リハビリを通じた身体機能の回復や自立支援は、患者の外見や身だしなみへの意識を自然と向上させ、相乗効果を生み出します。
身だしなみがリハビリのモチベーションを高める
身だしなみのケアは、単に外見を整えるというだけではなく、患者の心理状態や自己イメージに深く関わっています。
清潔で整った外見は、患者にとって自尊心を回復させ、自信を取り戻す一助となります。
特に、長期入院やリハビリ期間中は、身体的な劣化や精神的な落ち込みにより、自己イメージが低下しがちです。
身だしなみケアを行うことで、患者は自分自身に対する関心や愛情を確認でき、「自分も頑張れる」といったモチベーションの向上につながります。
上記のように、入院中に髪を整えたり、爪をきれいにしたりすることで、リハビリに対する積極性が高まったケースも多く、継続的な取り組みの重要性が示されています。
さらに、身だしなみの維持は、自己管理の意識を喚起し、日常生活の質の向上に直結します。
スキンケアにつきましては、以下の記事でも解説をしておりますので、ご参考になれば幸いです。
おわりに
身だしなみケアとリハビリは、密接な関係があるということが分かりました。
身だしなみの整った状態は、患者の精神的な安定や自己効力感が増し、回復速度の向上や退院後の自立支援にもつながっていくと考えています。
心と身体の両面からの支援というのは、入院患者さんの状況のみに当てはまらず、在宅介護や普段の生活にも当てはまる部分があるのではないでしょうか。
身だしなみのケアをする側も、される側も、身だしなみを整えることの先にある目的を考慮することが大切なのではないでしょうか。
この記事が医療者や病院に関わる方のみならず、少しでも多くの方の参考になれば幸いです。
【参考文献】
1)整髪が患者のリハビリ意欲や身だしなみに及ぼす効果、山口要子ら、大阪教育大学紀要 第III部門 自然科学・応用科学 63 (2), 15-22, 2015-02-28
資格講座の申し込み

「臨床化粧療法士®」になる為の資格講座やワークショップを随時開催しています。お化粧のちからで、より多くの方がいきいきと自分らしく活動できる社会を目指します。
前の記事へ
次の記事へ